25日都市から農業フォーラムが無事終了しました。
以下が議事録です。
○高安和夫挨拶
今年で2回目となる都市から農業フォーラム。
銀座では年間を通してミツバチを飼育している。
初めは西洋ミツバチのみであったが、日本ミツバチ合わせて10群いる。

第1部
○基調講演 講演者 原耕造氏 「屋上農園から気付く生物多様性」 NPO法人 生物多様性農業支援センター理事長
・市民農園。当時のドイツで勉強。日本の練馬区役所などで仕事に関わる。他農地などにも関わる。
地域の地権者に住めと言われ、かれこれ20年近く街づくりに関わる。
ソフトづくり(自治会)に携わる。
住民の方々をまとめつつ、ちいきの人々と仲良く暮らすにはどうしたらよいか。
・屋上農園から生物多様性。夏に白鶴酒造で生物調査を行った。
去年から銀座ミツバチと付き合い。
街の中の生き物はどうなっているのか。
原さんは日本中の田んぼをかけずり回っている。
・なんで生き物調査をしているのか?
消費者の方々は、産地を見られて新鮮、顔が見える関係ができ、安全安心。
作っている生産者は、10年ほどたつと、迎えるのが厳しくなってくる。
どうも本当の意味での会話が無いのでは?、と感じた。
いくら農業のことを消費者が知っているといっても、本質までは迫らない。
産地の野菜を食べ続けることが自分にとってどんな意味を持つのか、まで考えていない。
生産者は、買ってくれる人、ということだけで消費者を見ているのではないかと感じる。
蛍を見るために暗くなるまで待っている人。
なんで蛍なのか?千葉の銚子のほう。
孫に蛍を見せたい⇒農薬の種類を考えて、蛍がいる田んぼに変えた。
それをみんなで見ると、生産者と消費者という枠を(利害関係を)超えて、会話できる。
蛍を媒介として、蛍がいることで得られる安堵感を共有し、会話する。
これが生き物から見れるなら、生き物が共通言語になるのではないかと感じ、
農産物をつくる現場の生物物を作るだけの工場ではなく、そこの命を見る取り組み。
(消費者にとっても生産者にとっても)どんな生きいものがいて、
どんな関係を持ちつつ生きているのか?それから調査を始めた。
1:生き物調査4つの流れから起きる。人と人との交流で生まれた。
2:減農薬運動から減のう指導から始まったものがひとつ
(農薬を減らしつつ、きちんとした農作物をどのようにつくるか、という視点で)
3:生物の学校の先生が、自然科学の立場から、観察をすること。
4:国の行政から生じたもの。
来月名古屋でコップ10.
・屋上の米作りの現場にはどんなものがいるか。大手町の地下で野菜作り。
(地下で作る稲)虫がいないんじゃないか。それを自慢する職員。ちょっと違うのでは?
人間は多様な生き物の中において、存在していることをどのように気づかせるか。
大都会の銀座の稲作りで見られる生物はどのようなものがいるのか興味があった。
・来年できたお米で酒を作る。さまざまな生き物によって育まれてきたお酒である。
・ご飯をいっぱい食べると3000粒の米で、3株の稲。
3株の米があればオタマジャクシが35匹養える。
メダカ1匹はメダカを83杯だべる。
ご飯を食べることが、田んぼの生き物を育むことになる。
・来年4月からお酒を飲む御調子に、絵を描いたり、などを女子大生とプロジェクトを組んでやっている。
・生き物を通じながら、CRMをやっていく。
単なるCSRでなく、自分の作っている会社のものが、どのような生物と関わっているのか。
・屋上は、水流がつながらないのが難点。
・水田の多様性の話をするときに、水田が水を涵養するのはうそ?
水をどんどん流さないと台風のときなど大変。
洪水のときなど、貯めてたら大変なのでは。
・どんな生き物がいるのか実際に調査。結果はプリントに書いてある。
・右手で救って、左手のシュガーポットに入れ、白いトレーに乗せてどんな生物がいるのか調査。
(100円ショップで買えるものがどうぐ)
・街の生物100。このような本をもって街を回ると意外と生き物がたくさん住んでいる事が分かる。
多様性に目を向けていくことが一番大切。
・屋上緑化は20年くらい前から言われ始めた。
冷房効果を狙っている。かやぶき屋根は、日本の風土に合った建物。屋上緑化が広がるのはいいこと。
命の回廊、緑の回廊の都市での建設が課題となってくる。
・生き物は移動する。周りの環境をどうしていくかという議論が無いといけない。
緑化地1箇所だけではなく。
■都市生活と食糧安全保障
①ドイツのクラインガルテン
オーストリアの人が提唱。
ウィーンの市民が食糧不足になった際、市内の食糧供給を主な目的として行われた。
どんな木を植えるか、などを規制する。
プライベートとパブリックの市民農園には違いがある。
日本の市民農園では、食糧安保では、リンゴ何本、梨何本という規制がある。
(都市計画の中に組み入れられている、公的クラインガルテン)
②ベネチア
ベネチアは木の杭を打って、その上に作った都市。
繁栄していた時代には、海を伝ってもらっていた。
しかし戦争に負けてからできなくなり、食糧調達を自分たちで行うようになった。
ベネチアの場合、栄えているときは領土小さかった。
しかし戦争に負けてから、領土を買い入れ自国で食糧生産。
③イギリス
インドなどの植民地から食糧を輸入していた結果、航路が断たれたとき、餓死寸前に。
戦後は反省を生かして80パーセントほどの自給率を誇る。
④キューバ
有機農業の先進国。
キューバは自国での食糧を作らざるを得ない⇒必然的に、自国で有機農業をおこなうようになった。
■都市生活者の農業観
・ドイツの人はどうして自分の地域のリンゴジュースを飲むのか。
私たち日本人が飲んでるのは中国産。
自分たちが自国のリンゴジュースを飲まなくなったら、自分たちの国のリンゴが切られて無くなってしまう。
景観と、そこに住んでいる誇りのために、じぶんたちのリンゴの畑を食べる。
(可視領域の食べ物を食べていく)
・ドイツの街の景観が美しいのは、人から見える空間に花が植えていなかったり、
ガラスが汚れていると、訴えられてしまう。
市民全員の事を考える意識があるため、景観に対する意識がその点で日本と異なっている。
・ドイツのマクドナルド看板
街並みが茶色なら、その配色を崩さない工夫をしている。
自分が見てどうか、でなく他の人から見てどうなのか・
・農のある街づくり・・・
矛盾に気づいてほしい(プリントより)農業を語るときに、プリントの右側の議論しかしていない。
お金の単位で技術を進めている。
農業生産をする傍らで、命の単位の生産をしている部分への国民の議論があまりない。
左側の議論をやっていくべき。他の生き物をひっくるめた農業をする事が大切。
(お金に換算できない価値・・・愛、家族、友等)
■都市のうちの持続性の限界
都市農地と農家は絶滅危惧種である。
現行の法では、どうしてもそうなってしまう。
・一物三価・・・原因は都市の農地ではないにもかかわらず、改正生産緑地法ができてしまった。
・今は農地を残していける状況ではない。
今までは緑地空間、食の生産地という観点しかなかったが、これから生物多様性の視点を入れていってもいいのでは。
・生き物の回廊。平面緑化も屋上緑化も21世紀の屋上緑化として、街に生き物が多様であることは当たり前で、そこで生きていくことが大切。
○高安
ミツバチを通して街で自然を感じることができ、このようにフォーラムに人が集まるようになった。
10分休憩
第2部
○事例発表 2:15~ 司会 藤崎健吉氏(藤崎事務所)
・プランナーであり、農学系出身者
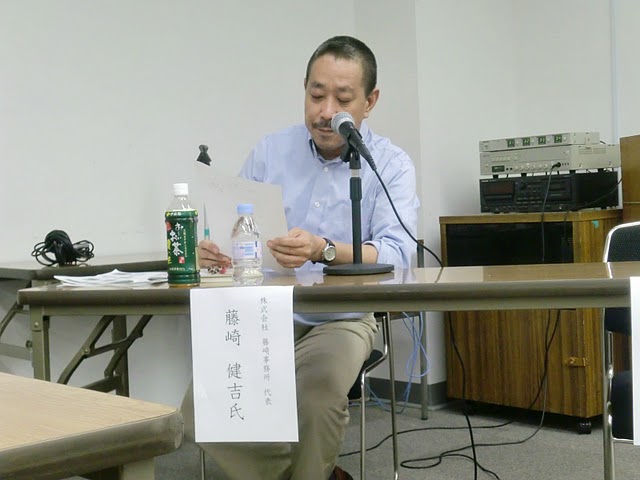
○札幌ミツバチプロジェクト代表 酒井秀治氏

・酒井さんは街づくりのコンサルの仕事。
都市の広場の設計のコーディネート、地域の宝物を登録したりなど。
まちづくりを中心としたミツバチプロジェクトにしていきたい(まだ始まったばかりで5月スタート)
・街の緑をもう一度作り直し、蜜源調査などで街の自然に気がつくこと。
ミツバチが3~4kmとぶので、札幌でしかとれない蜜を。
市民に開かれた形でどこまでできるようチャレンジする。
・最北端のミツバチプロジェクトは銀座をモデルとしてスタートした。
田中さんなどにお話しを頂きつつ、決行した。
巣箱は、現在3箱。現在6万匹あまり。
・札幌ミツバチプロジェクト実行委員会以外にさっぱちボランティアなどに支援してもらう。
初めは、札幌の養蜂家に手伝いを頼んだがなかなかオーケーもらえず。
新聞に出てからようやく手伝う人が現れた。
・市民に開かれた活動にするため、内検や、ミツロウづくりも市民の方に参加してもらう。
・緑が多いイメージあるが、実は少ない。
市民の力で、どれだけ緑を作り出せるかが課題。
小さいながらも菜園、プランターの設置もづつ行っている。
意外と野菜作れて、それと蜂蜜を合わせて、ワークショップなども。
・コラボをする形で今いろいろ売り込みをしている。
また、美容と健康というコンセプトで石鹸を作ったりしている。
どの石鹸が一番いいか?などモニターにもなってもらう。
また、子供や大人にデザインを出してもらったりしている。
・そのままのハチミツをドーナツやアイスにかけたりしている。
今年6月から、12回程採蜜し、20~30キロはコンスタントに採れた。
今年は合計300kg採れた。
(1はこ100kgほど。)糖度は80%こえる。
その時期その時期でハチミツを通して四季を感じる。
・来年時期の課題
ボランティアのチーム編成や、助成金でなく、自分たちで事業としてやっていくように。
ミツバチを置く場所を屋上に作ること…今は自由に入れない。
養蜂業に登録していないので来年時に加入。
札幌プロジェクトは役所の赤レンガ(役所)、札幌ハニーエンジェルスとの調整も必要。
・これから北海道の食と銀座がつながれば面白いかもしれない。
○質問
Q初めはどのくらいの規模だった?
A3箱。蜜源が周りにたくさんあったから採れたのだろう。
○東京画廊代表取締 山本豊津氏
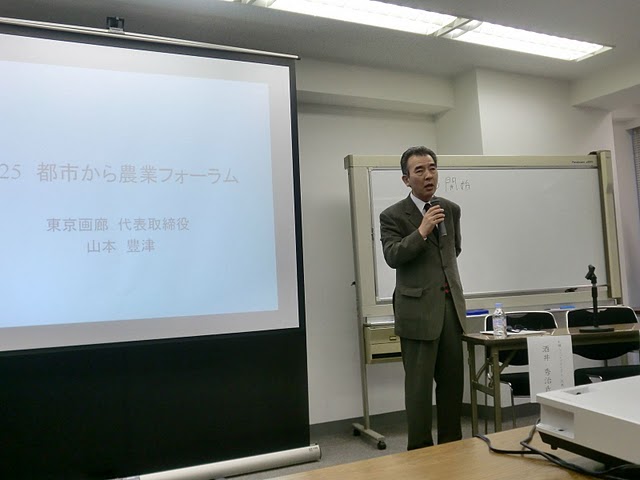
・旦那の遊び、と考えている。一番感じたのは、男性が三味線など文化的遊びをしなくなった。
街から離れたところで遊んでいると、街の香りが無くなる。
アメリカと違って日本にはゴルフの文化が無い。日本は石川遼に集約されてしまう。
大人が街で真剣に遊ばないとダメ。これが単純な動機。
8平米程度の菜園を東京画廊に作る。
日本で菜園がある画廊はここだけ。ヒトがやらないこと大好き。
・朝鮮落花生を植えた方がいいと進められる。
(むかし朝鮮通信使が持ってきた)私たちが現在食べてるのはペリーが持ってきたもの。
・普通の農業に戻っても生きていけない(山本さんに進めた人)
・絵が分かるのは、歴史的な背景が分からなければ無ければ、意味がない。
例えば、印象派の絵は、浮世絵の影響を受けている。浮世絵を海外の人の絵を通して見ている。
・農業に美の概念を持ち込む。美味しいものが食べたい、という別の観点を持って食べている。
美味しい、という概念と美の概念は近い。美しいと思うのは、遊んでいるから。
仕事というほどの生産性ではないが、遊ぶつもりでプロジェクトを作った。
画廊の目の前の和菓子の老舗、万年堂・・・朝鮮の「おめでとう」というお菓子をまだうっている。
しかしこれが朝鮮のお菓子と思っている人はほとんどいない。
このお菓子をお土産にしたらすごく喜んだ。歴史が詰まったお菓子である。
・おめでとうを作っているのが若い職人。
和菓子は、昔はお茶会のときに自分のオリジナルなものを注文していた。
1こ300円で作るから15000円で50こ作る。
ちょっとした道楽ができる。
この人に朝鮮落花生でお菓子を作ってもらう。
・らっかせいの殻の紫まで生かしたい。
おめでとうは300年続いてきたからそれは残し、これから300年続く菓子を作る。
・銀座はアウトプットの街。銀座が遊びを付加していけばいい。
・一つの菓子をつくるために、植えるものを相談したり、ハチのお休み処になったり、いろんなことがある。
・ハチがうちに来て休んでいると、人の家の子を預かっている気分になる。かわいい。
・気をつけることを気をつければ、画廊の職員は誰も刺されない。
・日本人が遊びを真剣に考える時代に。プロはこのような遊びはやらない。素人だから遊べる。
・アートは素人が新しいことが考える。ただし素人は新しいことを気付かない。それをパクる玄人。
・農業者が銀座をパクればいい。
・価値は3種しかない・・・素材と技術とコンセプト。
・例えば、寿司・・・西洋人の料理の概念とは異なっている。素材が美味しければ、料理は必要無い。
・日本人の宝とは・・・・漆、紙、木でできたもの(金、銀、ではない)これをたくみな技術で作り上げる
・コンセプト・・・何を作ればいいか。世界の情報の把握がコンセプト。美術は、コンセプトに向かっている。
これを農業にも生かすべき。
・遊びは職種や年齢を超えていく。遊ばないと結びつかない世界が銀座に。札幌や新潟の人が遊びに来る。
そのような関係がこれからの物作りに必要。
Q朝鮮落花生はどのくらいとれる?
Aあんまり聞いてほしくない・・菜園はあまり。(笑)
これからハーブをつくって近所の料理店にわけ、仲介役として関わりたい。
○田中淳夫
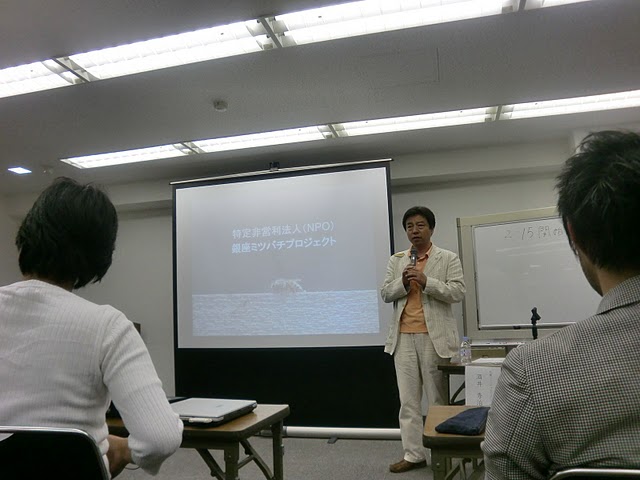
・昨年札幌からミツバチを飼いたいといったとき、できるよ、といった。
安易に言ったわけではないが、
ミツバチを飼ってハチミツを採って地域を応援をするプロジェクトにすればいいのではないか?と提案した。
ここまで大きくなるとは思わなかった。今年3箇所も札幌で始まった。
・5年前に高安さんとミツバチを飼うときは、馬鹿なことしたな、と思った。
「まさに知性を身体化したアートである。」と言われた。
・100年以上つづく日本の養蜂の歴史の中で、アートと絡めたりするのはさすが銀座。
・ガイアの夜明け・・・銀座産のはちみつを使ったお菓子など(松屋の生きのこり戦略)
・地域の皆さんとつながって、「ミツバチが農薬に弱いから地域に農薬使うな。」というのではなく、
農薬を極力使わない生産者を応援するファームエイドを開催。
・茨城、岩手、福島などさまざまな地域とつながる。
・おんでこ・・・・新潟の文化。食べ物と文化がリンクしている。宇和島の牛鬼も。
・銀座ビーガーデン・・・農ごっこのあそびのようなもの。でも収穫祭などでコミュニティーの形成。
・何も無かった銀座の屋上に人のコミュニティー=銀座の人の生物多様性。
企業名から、本名を呼び合う仲に。一流の人々がつながっていく。
・【佐渡のトキのために作ったお米】
屑米として処理されていたものを、買い取ってロールケーキなどになる。
しかしそれを銀座で商品にすることで、売れる。
・一生のうちで一度銀座でハサガケしたい・・・夢がかなった!
・酒米をイタリア料理屋でリゾットに。(銀座のはさがけした米から)
・ジャガイモをスワンベーカリーの福祉作業所の人々につくってもらい、収穫した(1.5トン)
・地域、街とつながってさらに福祉までつながることで、単体では解決できない問題まで解決できるのでは?
命のつながりを感じ、アートとつながれば、いきづまった
社会が大きくて広がりのあるものにかわり、新しい社会が見えるのではないのだろうか。
第3部 パネルディスカッション
テーマ「農を取り入れたまちづくり」
○司会 藤崎氏
街に生命を取り組んでいくこと=農を取り入れた街づくり(原氏)
Q初めてみて感じたこと
A酒井・・・5月の初めに札幌にミツバチがやってきた。ミツバチの群れた状態を見たのは初めて出会った。
近くで蜂を見てもらう機会を都市の中で作っていけることが良かったとストレートに感じる。
A山本・・・目の前に畑があることで、歴史を語れる。
たった8平米でも、生産量は上がらなくとも、話の種の方が良くできる。
若いアーティストや従業員の皆さんも生活のリズムを作れる。
(ただ仕事のみでなく)コミュニケーションとして意味がある。遊びを通じて学べる。
遊びはルールを知るために必要。ルールから秩序等が生まれる。
モノづくりは遊びにつながり、秩序や社会基盤ができる。縦のつながりが横につながる。
藤崎・・・田中さんに対して。進化しているプロジェクトの経緯をかいつまんで
なぜ銀座でミツバチを?
田中 養蜂家の場所をかして場所代としてハチミツをもらおう、と考えていたが実際にやることになり、
面白いようにとれた。
せっかくだから自己消費でなく街につなげよう。商品として定番となるまでになる。
このごろ有る意味義務的にハチミツを作るようになっている。もうあともどりできない。
藤 この1年を通して、リアルになっていった。世の中を動かすムーブメントになった
田中 お祭りのときにハチミツ提供したりはあったが、
今年から銀座社交料飲協会とつながって、ハニハイをつくる。
一流のバーテンダーがひろめる。これを飲むことで緑化が進められる。
スタートのときに冗談だったことが現実化する銀座の街のすごさ。
藤 銀パチはアートだ、というのも体現されている気がする。
藤 少し話を変えて、これから生産者をどのように応援できるか、都市から農業を行う意味を聞かせてほしい。
(生物多様性に気がつく、また、生産者とつながる)
原 物を買う関係だけではなく、銀パチは消費者と生産者という関係ではなく、
街から農業の良さを発信する楽しさのために、地方からわざわざ銀座に来る。
自分たちの再認識のために地域の人が銀座を訪れる。
藤 どんなインフレをそだてられる?
酒井 中学2年生が養蜂家になりたい、といって札幌の養蜂家と交流するなど。
北海道の食糧自給率は高いが札幌の自給率は低い。
自分たちのやっていることを楽しくアピールできる場の提供ができたらいいかもしれない。
北海道の中の札幌としてのつながり。
藤 ハチミツで北方領土とつながるってどうやるの?
田中 渡辺さん・・・ミツバチは愛。
生き物の中でいえば、巣枠のなかで働いていないミツバチがいても、隣のミツバチは怒らない。
排除でなく、取り入れていくやさしさを。
小さな生き物に対する配慮などでいままで見えなかった関係が見えてくる。
藤 農業は楽しくなくてはいけない、というとき、都市農業をアートとして取り入れるためのヒントは?
山本 ラオス・・・近代化無理。中国は都市化していく。
中国は近代の終点まで来た。自然観、世界観は西洋人と日本人では違うのではないか。
素材に対する感覚は西洋と日本人では違う。
西洋は言語的知性(言語を中心としたもの)日本は身体的知性。
近代というものをどのように考えるかという時に、アート的考え方の方が分かりやすい。
国の政策としていいかわからないが、農村を国有化する。
江戸時代にもどせば、生産物を作るだけでない価値が生まれるのではないか。
自然をもう一度考え直して、アーティスティックに考え、作り直す。
こうすることで自然に対する考え方が変わる。
藤 8平米の菜園しか持っていない人の意見にはきこえませんね(笑)
銀パチは世の中動かしててしまうところまでいくのでは?
原 自然は明治維新で初めて自然という概念が入ってきた。
ネイチャーを表す概念はなかった。
江戸時代までの日本人は、海も川も含めた流れの中に、人間は存在している、という考え方をしていた。
今の私たちは、自然と人間の差別化。西洋の自然はデカルトの二元論以降、
価値観の大転換や産業革命などを経て、現在の自然観に。
中国の(漢人の)みんぞくは西洋と同じ畑作の民族(稲作ではない) ミツバチとともにわれあり、
という価値観が大切。
藤 私たちの中の農的なものをどう引き出していくかが大切。
藤 農的活動を行っていきたい人間が、都市・都市近郊農業をどのように盛りたてていけばいい?
原 戦後の後に作られてきた法では無理である。
160000人の市民がそこに命があり、自分や自分の子供の命を削られるような感覚を持つことで、
市民税を余計に払いつつやっている横浜のように、市民の中から活動を起こしていくこと。
藤 国が動いて農を有るべき姿に戻す山本さんの意見もいいが、市民から活動を起こしていくことも大切
藤 これから具体的にどのような目標で行っていく?
酒井 10箱に増やすビジネスをしようとしているところもある。
私たちは街づくり、大人の遊びとしてやっていくことがベースにあるので、
まず養蜂登録をしたうえでいろいろな商品を対策していく。
農業とか生産で考えると、敵対関係になるが、そうではなくて競い合う、共に働く関係を作りたい。
ハチミツのとりもつ縁を作りたい。
商売にするととたんにつまらなくなる
山本 8平米でどれだけ大ボラふけるか。
伝統文化(茶道、華道など)が農業から生まれた、ということをみんなで話し合う。
おしゃれな農業運動。生け花の起源(仏教と神道)
水田の脇にいける花(神と人民をつなぐ橋)。
花を水田に植えるアーディスティックに展開していく運動などもしていきたい
せっかくあそんでいるのであるから。
天皇制があり、こんなにアーティスティックな国はない。銀パチを宗教法人にしたら?
田中 政党をつくろう、と想像を超えたご提案。これこそ遊び。
銀座で農業、養蜂。プロからすれば排気ガス臭い、ミツバチかわいそう、といわれる。
有名な養蜂家の人が、地域ではなかなかとれないのに銀座で採れて悔しい、といった。
ミツバチが地域では安心して暮らせないのか?
ラベイユからの折り紙つき。
社会が、持続できないものを無理して続けてきた。
江戸時代は400年の歴史がある。銀座に持っている知性が集まっていた。
現代の銀座でも同じことがおきてきている。
世界のメディアが、やってくる。銀座に大きな可能性を感じている。
いかに持続可能なミツバチ飼育ができ、街の皆さんに受け入れてもらう環境を作っていけるか。
街の皆さんがこの場を利用して遊べるように。
藤 今日のお話はどうでした?
原 田んぼの生き物数えてあほじゃないかといわれて15年、何事も粘り強くやっていくことが大切。
5668種の田んぼの生き物の票集めれば・・・政党作れる?(笑)
ミツバチも田んぼの生き物。
百姓に自分の田んぼの蜂を良く見ろ、といっている。
この連鎖がつながっていけば・・・輪の広がりが一番大切ではないかと思った。
藤 今日はとてもよかった。新しい時代の新しい都市農業の可能性を感じた。
都市から農業フォーラム終了 16:00
交流会は紙パルプ会館1階パピエで行いました。

銀座社交料飲協会緑化部の白坂亜紀様と清水桃子様に乾杯のご発声をいただきました。
和やかな素敵な会となりました。
ご参加頂いた皆さま、ありがとうございました。
気が早いですが、次回の都市から農業フォーラム3月26日(土)になります。
3月になればミツバチのシーズンもスタートすることと思います。
フォーラム議事録作成:藤原あゆみ
写真撮影:登彦雄
ブログ校正:事務局高安

